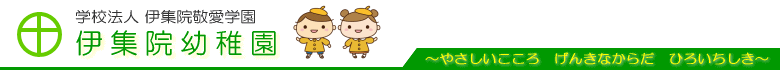幼稚園だより(月報) 2015年8月

伊集院キリスト教会 牧師・園長 麦野達一
「お友達とは仲良くしなさい」これは親であれば誰でも子どもに教えたい、伝えたいことでしょう。ただ「共に」生きるということはいつでも「仲良くできる」とは限らないことです。幼稚園には120名近い子どもたちがいます。友達同士仲良く、微笑ましく遊んでいる子がいる反面、些細なことでぶつかり喧嘩をしている子もいます。どちらも幼稚園の日常です。喧嘩をしている子どもたちに大人はなんと言うでしょう?「仲良くしようね」と言うでしょう。すぐには無理でも、辛抱強く子どもと向き合い、子どもの気持ちに寄り添い、一つ一つ思いを受け止め、こちらの気持ちを伝える時に子どもの心が変わる瞬間があります。その時「仲直り」は実現します。ぶつかりあった双方が自分の気持ちを丸くして相手の存在を受け止めた時に仲直りできるのです。そしてそれを「平和」と呼ぶのではないでしょうか?
いま私たちの国の「偉い人」たちは、「仲良しの国」と「仲良しでない国」とを分けて、仲良しの国が仲良しでない国に意地悪や暴力を受けた時には、仲良しの国と一緒になって仲良しでない国をやっつけてやろう、という法律を作ろうとしています。「偉い人」たちもこのような身近な例を引き合いに出して、「友達がやられそうになったら一緒になって戦うでしょう?」「それが当たり前だよね?」と国民に説明しようとしています。
でもよく考えてください。子どもの喧嘩と国と国の戦争は違います。喧嘩(戦争)に至るプロセスも、そこで起こる出来事も全く違います。国は戦争にならないために普段から関係を持ち、対話を重ねて良い状態を作り上げるのです。それが外交です。戦争は子どもの喧嘩のように突発的に起きるわけではありません。必ず背景があるのです。もちろん子どもの喧嘩にも背景はあるでしょう。だからその背景を丁寧に解きほぐしてあげるのが大人の仕事です。いま私たちの国の「偉い人」たちはこの解きほぐしではなく、戦いに向かおうとしています。そしてその戦いの場に送り込まれるのは・・・・
私は3人の男の子の父親として、牧師として、園長として、安保関連法案の廃案を望みます。
8月のテーマ「たのしい」
伊集院幼稚園主任教諭 美園実保
夏休み、お母様方、お父様方にとっては、やっと7月が過ぎた!という感じでしょうか?本当に、お疲れ様でございます。毎日のお食事の献立、暑さと洗濯物の多さに負けてしまいそうですよね。
幼稚園のひよこでも、毎日、水遊びが繰り広げられています。ホースから出る水しぶきにキャーキャー言いながら、走り回っています。楽しいの一言です。先生も楽しそうです。
お家でも、カーポートやベランダでの水遊び、お友だちやいとこたちが集まってと、楽しい夏は、お金をかけなくても演出次第で、キラキラ輝き出します。そのためには、寄り添う保護者に楽しむ心があってのことです。
どうしても出来ない日は、助けを求めましょう。そして、早めに休み、明日に備えましょう。多分、子どもたちは、家族や保育者とゆったりと過ごせた時、だいすきー、おもしろい!楽しい!の気持ちを表したくなると思います。子どもたちが大きくなった時、素敵な思い出として蓄えられるのです。
思い返すと私自身も良く父が、遊んでくれました。そして、今老いた父に思い出話をすると、いつも決まってこう言います。「お父さんが遊びたかったんだよね。子どもたちのおかげで堂々と遊べるからね。」確かに。子どもたちがいなきゃ、始まらないのです。水遊びがしたくて大人が一人でしてもさびしさが漂います。自分が、子どもの頃やり残した遊びや行きたかった所に行くも良し。自分が楽しく過ごせる企画をして、家族に喜ばれて、プラス愛する奥さまが喜ぶことになり、優しいお母さんでいられるのです。そこに心の余裕が生まれます。そして何より子どもたちに優しくなれるのです。このステキな循環を助けあって築いていきましょう。神さまが与えてくれたパートナーですもの。夫婦が互いを思いやることが、平和な家庭をつくるのだと思います。そして、世界の情勢にも眼を向ける視野をもって、毎日の目の前にいる子どもたちを愛していきましょう。この平和をつくる心を大切に残りの夏休みを楽しく過ごしていきたいものです。お互いに…
輝くあなたのために(5)~子どもの手本に~
伊集院幼稚園教諭 麦野節子
今年度は、「置かれた場所で咲きなさい」(渡辺和子著)をもとにみなさまと幸せな生き方を分かち合いたいと思います。
毎朝5時になるとトントントンとまな板の音。おいしいみそ汁の出来上がり。孫娘たちがよろこんで食べてくれるので、ばぁばは毎日作りました。
山のような宿題を娘(母親)と孫たちがやっています。姉は我慢強く、ため息をつきつつがんばります。妹は、もー、わからない、ワーッと泣きます。それを娘はなだめすかしてさせています。
子どもは親や教師のいうとおりにはなりませんが、親や教師のするとおりになります。
いつの日か彼女たちが母親となった時、同じように食事を作り忍耐強く子どもと関わる母親であってほしいと願いつつ…
よき手本とは、一日一日を子どもの存在を喜びつつ神さまに感謝して過ごすことではないかと思います。